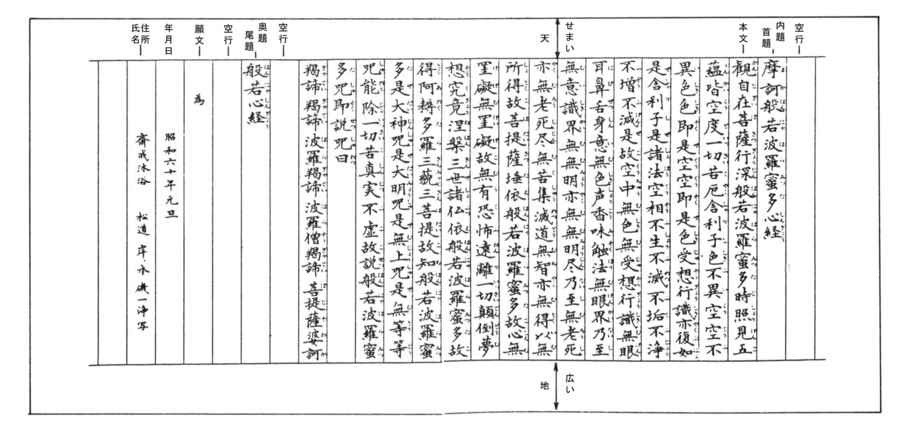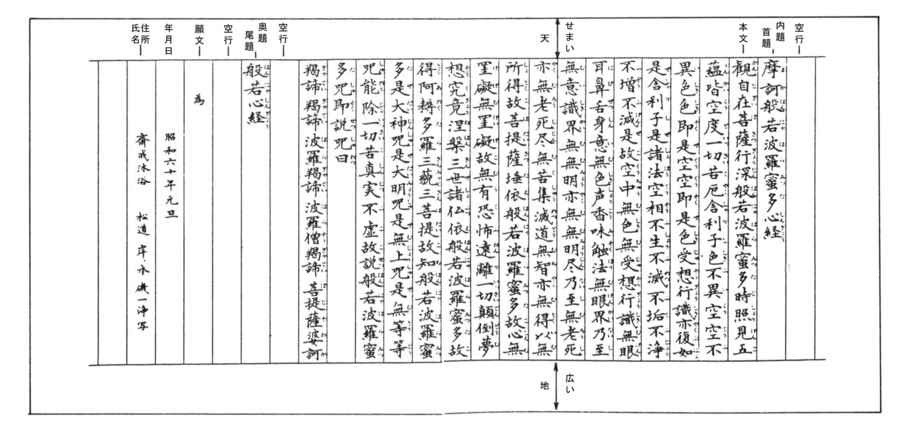京都にある写経司。般若心経・写経グッズを取扱しています。写経用紙・写経セット等、写経用品はこちらで。とりあえず写経を始める方にお勧めです。写経の作法・方法・様式をまとめてみました。
ホーム>写経の作法・様式

ご自宅での写経の作法・写経の方法・写経の様式(般若心経)
1.手を洗い、口をすすいで身を清める。
2.香をたき、室内を清める。
3.墨をすり、心をしずめる。
4.合掌礼拝
5.願文読誦
真言は不思議なり、観誦(かんじゅ)すれば無明(むみょう)を除く。
一字に千理を含み、即身(そくしん)に法如(ほうにょ)を証す。
行々(ぎょうぎょう)として円寂(えんじゃく)に至り、去々(ここ)として原初(げんしょ)に入る。
三界(さんがい)は客舎(かくしゃ)のごとし。一心はこれ本居(ほんこ)なり。
我、今至心(ししん)に懺悔し謹みて般若心経を写経し奉る。
仰ぎ願わくは、一字一文(いちじいちもん)法界に遍じ
三世十方(さんぜじっぽう)の諸仏に供養し奉らん。
6.浄写(無我の境地に入り、至心に写経する)
写経の様式
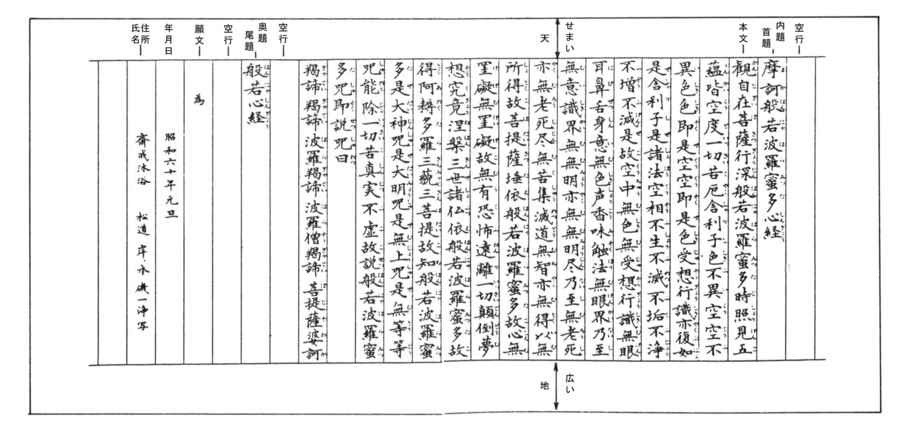
〔天地のあき〕
写経用紙には、せまい方を天(上)に広い方を地(下)にします。罫粋があり天地の広さが
ちがいます。
これは、経典を尊崇する意味で、古くから行われてきた様式に従っているのです。
〔内題(首題)〕
一巻を代表する経題ですから、省略せずに正式名称で書きます。
<例>摩詞般若波羅蜜多心経
(真言宗系では仏説が加わります)
長文の場合も一行につめ、しかも文字が小さくならないように書き、下に余白を持つのが、
正式の法式です。
〔本文〕
一行十七字づめが約束。これは、唐代の初めに統一されたと言われていますが、十七字にこ
だわらないものも少なくありません。
〔奥題(尾題)〕
省略した題名が、よく用いられます。
<例>般若心経
〔願文〕
祈りをこめて書く写経には、巻尾に願文を書きます。年・月・日、姓名、写経の場所、誰の
ため、という様式です。
修養や書道としての写経なら、願文を書かなくて結構です。
〔空行〕
内題の前、本文と奥題の間、奥題と願文の間、巻末などに空行をとることは、古来からの様式
で、美的効果の上でも必要です。
〔誤字、脱字の処置〕
脱字を見つけたときは、そこに筆先で黒点をつけ、脱字を行末に書きます。二字脱字なら、
二点をつけます。
誤字は、本来、はじめから書き直すべきですが、誤字の右肩に黒点をつけ、その行の上また
はそばに、正しい字を書けばいいでしょう。
7.祈念(それぞれの願いごとを書き、念ずる)
8.般若心経読誦(合掌)
(浄書したお経に目を通しながら唱える)
9.般若菩薩真言 三返
オン ヂシリシュロタ ビジャエイソワカ
10.回 向
願わくば此の功徳(くどく)をもって
普(あまね)く一切に及ぼし、
我等(われら)と衆生(しゅじょう)と
皆ともに仏道(ぶつどう)を成(じょう)ぜんこと
11.合掌礼拝
12.退 座
浄写された写経用紙は、お近くの寺院に御奉納されると良いでしょう。
|佐|藤|文|庫|までご送付下されば、御希望の寺院(京都市内)に御奉納させていただきます。
お気軽にお申し付け下さいませ。 合掌。
●般若心経 写経の手引きはこちら。 初めての方に最適の解説図書です。お申込は購買部から。
●写経用紙(般若心経)の頒布はこちら。 初めての方に最適なトライアルセットです。
copying of sutra




S A T O B U N K O
|佐|藤|文|庫|に関するお問合わせは
こちら
から
Copyright©copying of sutra SATOBUNKO 1997